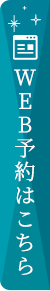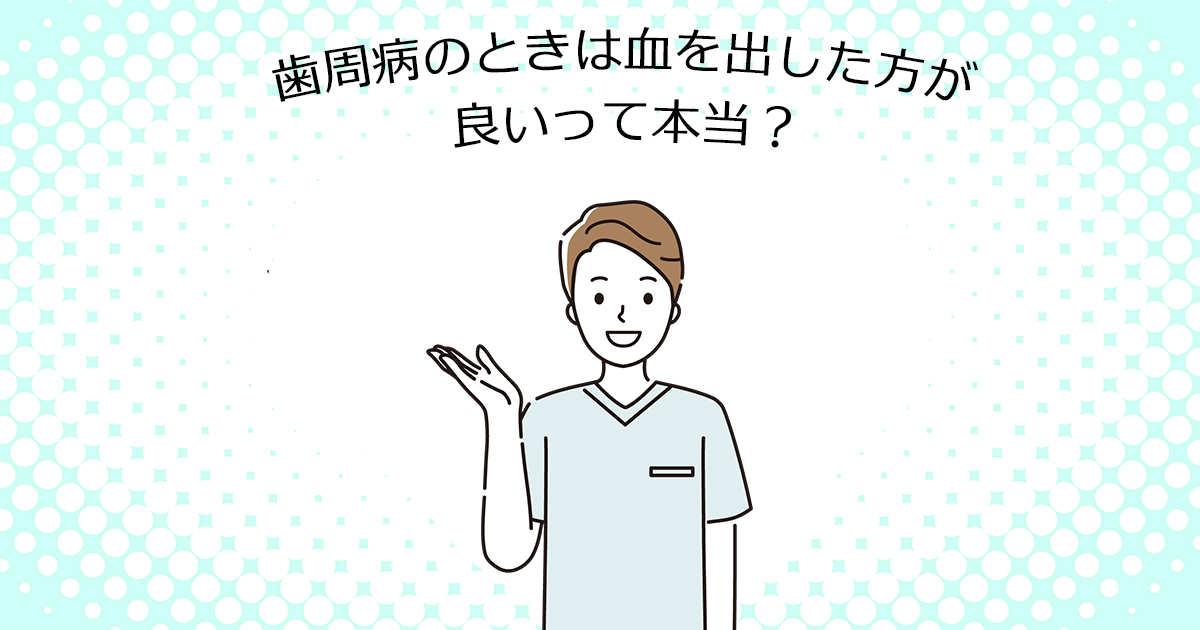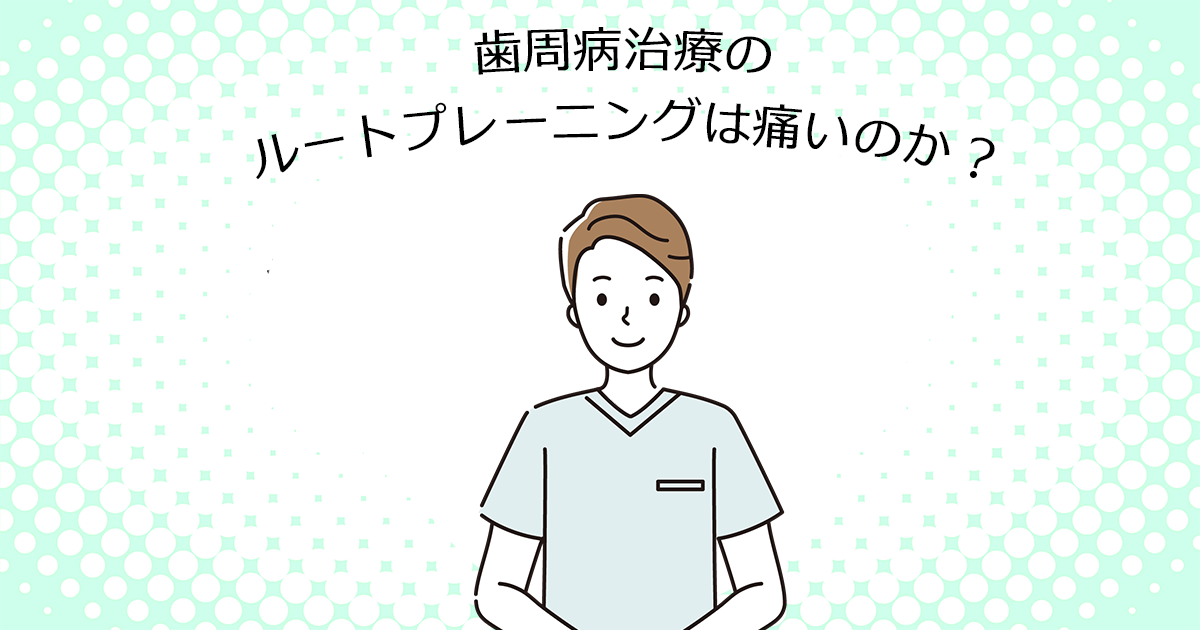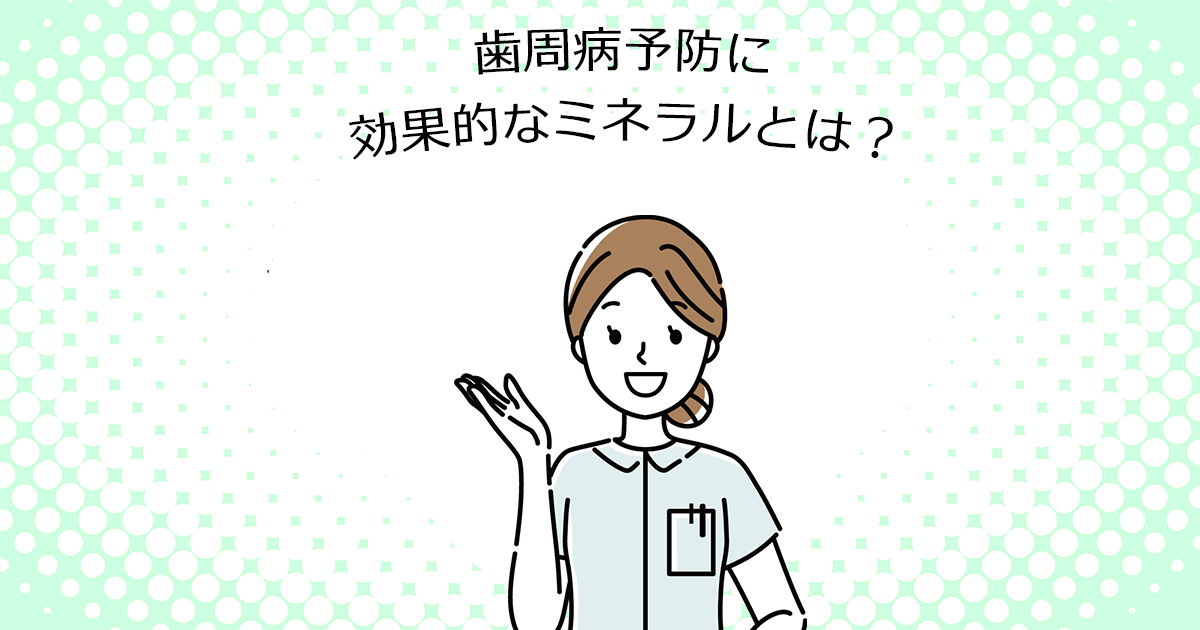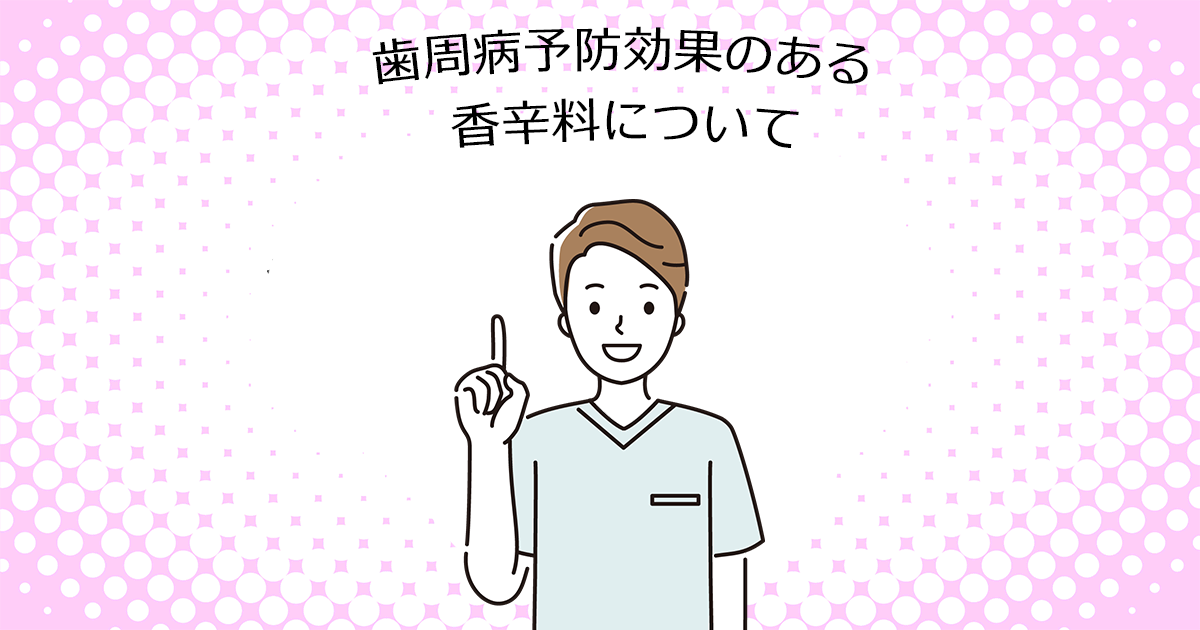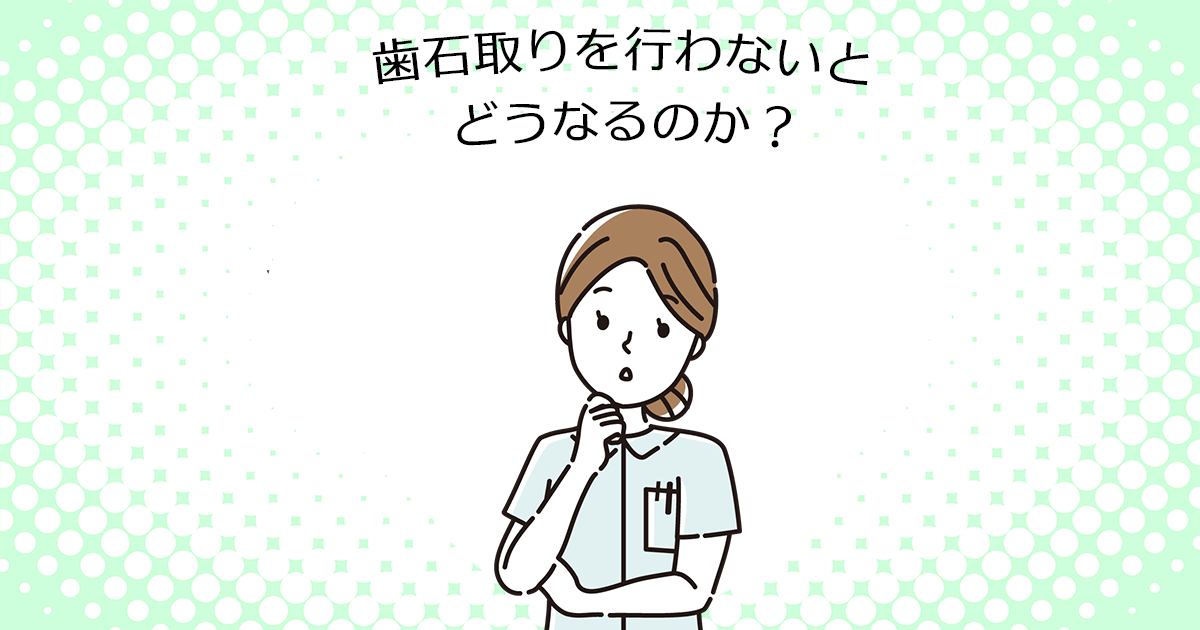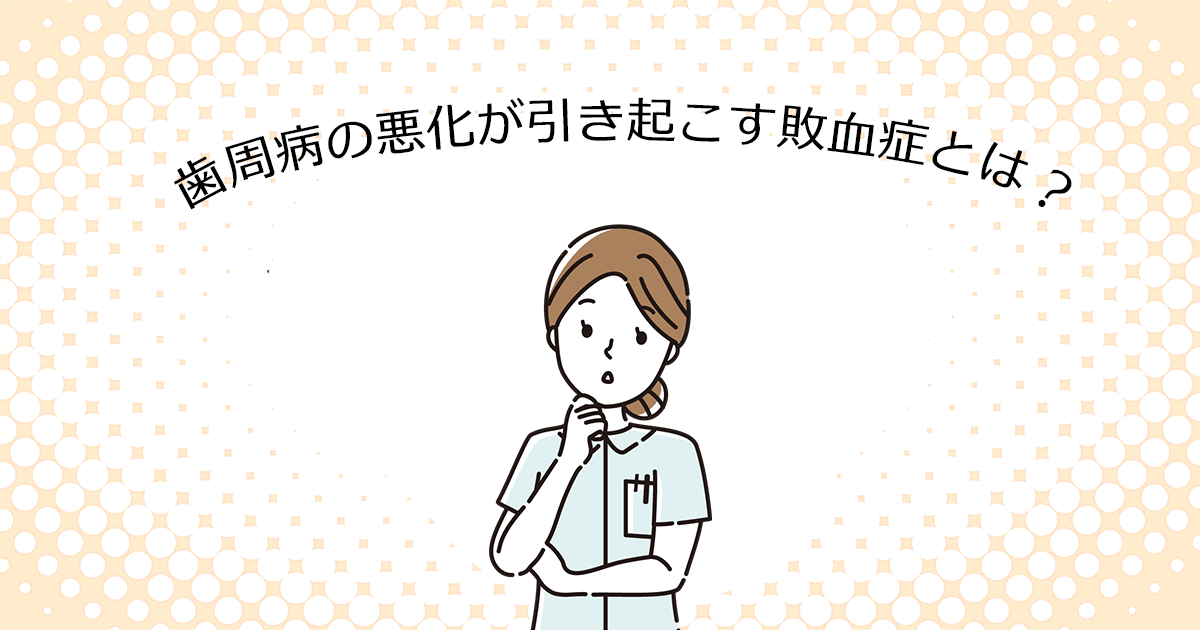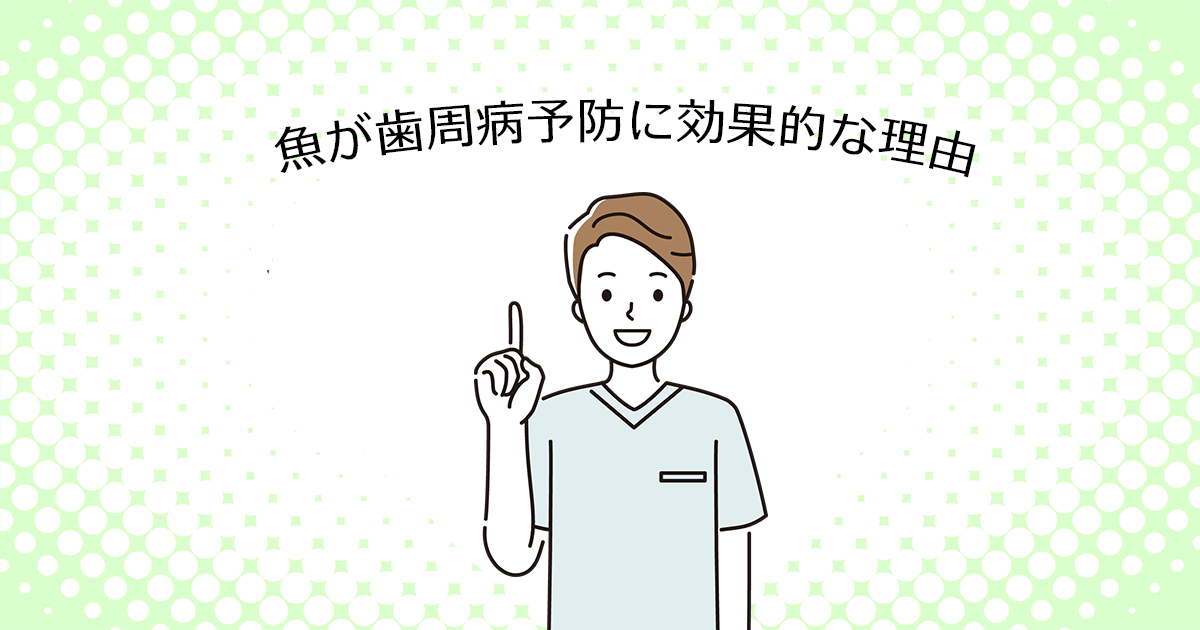歯周病の主な症状に、歯茎からの出血が挙げられます。
こちらは主に、ブラッシングを行ったときの刺激が原因で生じるものです。
また歯周病のときは、歯茎から血を出した方が良いと言われることもありますが、これは果たして本当なのでしょうか?
今回はこちらの点を中心に解説します。
歯周病の血は出した方が良いって本当?
歯周病のときの出血は、“出した方が良い”というよりは、“出しても良い”という認識が正しいです。
冒頭で触れた通り、歯周病における歯茎からの出血は、主にブラッシングの刺激によって生じます。
このとき、出血するのを恐れてブラッシングを控えるという方もいますが、これでは歯周病の症状は改善しません。
たとえ出血があっても、ブラッシングを行ってプラークを除去したり、歯茎を適度にマッサージしたりすることが大事になってきます。
歯周病のときの正しいブラッシング方法
歯周病の症状がある程度進行している場合、いつも以上に優しく丁寧にブラッシングをすることを心掛けます。
具体的には歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目に当て、小刻みに動かします。
このとき出血しても構いませんが、ゴシゴシと強く磨くのはNGです。
また歯と歯の間にも、炎症の原因となるプラークが溜まっているため、歯間ブラシやデンタルフロスを使用してキレイに清掃しましょう。
怖がらずにブラッシングをして出血させることで、歯茎の新陳代謝や血行が促進され、腫れや炎症を抑える効果が期待できます。
悪い血を飲み込むことのリスク
歯周病によって起こる出血は、むしろ積極的に起こしていくべきですが、こちらのいわゆる悪い血はなるべく飲み込まないようにしましょう。
歯周病が進行すると、歯茎から毎日おちょこ1杯分程度の血液が出ます。
こちらは歯周病菌が含まれているため、体内に入るとさまざまな疾患の原因になります。
例えば歯周病菌が気管に入ることで、呼吸器系の疾患を引き起こすリスクが高まります。
さらに、糖尿病や心臓病、早産や低体重児出産といった疾患につながることもあります。
そのため、ブラッシングの際に出た血については、歯磨き粉などと一緒にしっかり吐き出します。
まとめ
歯茎からの出血は、放置すると歯周病が進行する危険なサインです。
出血が見られる場合、しっかり血を出してブラッシングをするだけでなく、根本的な治療を受けるために歯科クリニックを受診することが不可欠です。
歯科クリニックでは、ブラッシングだけで落としきれない歯石を除去してくれたり、正しいセルフケアの方法を教えてくれたりします。