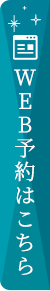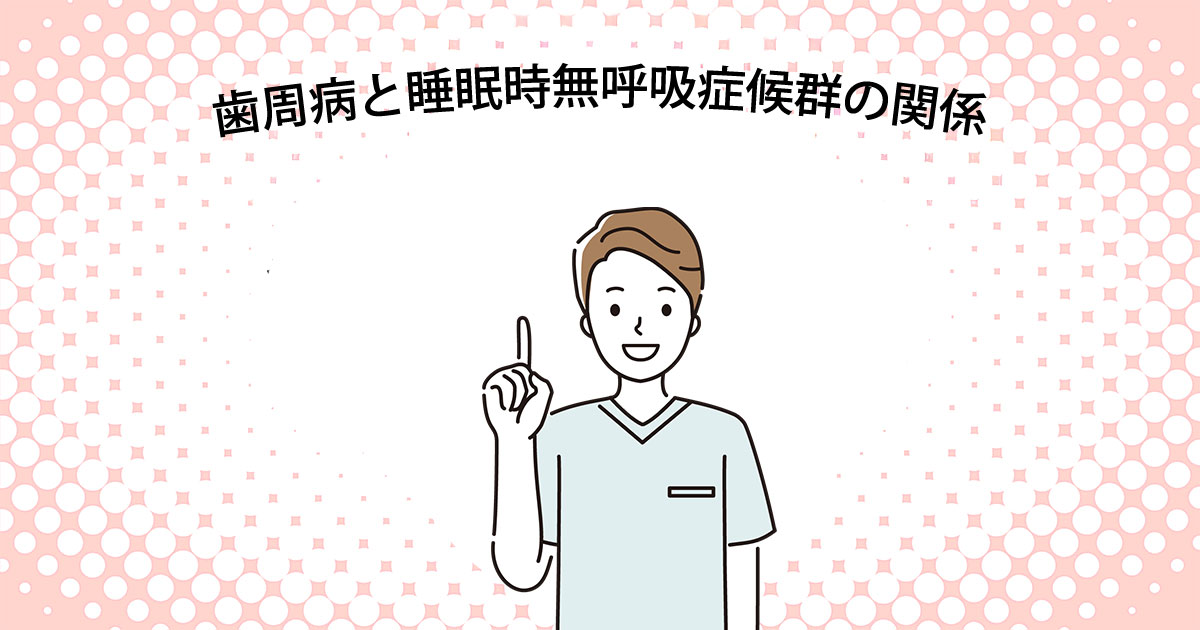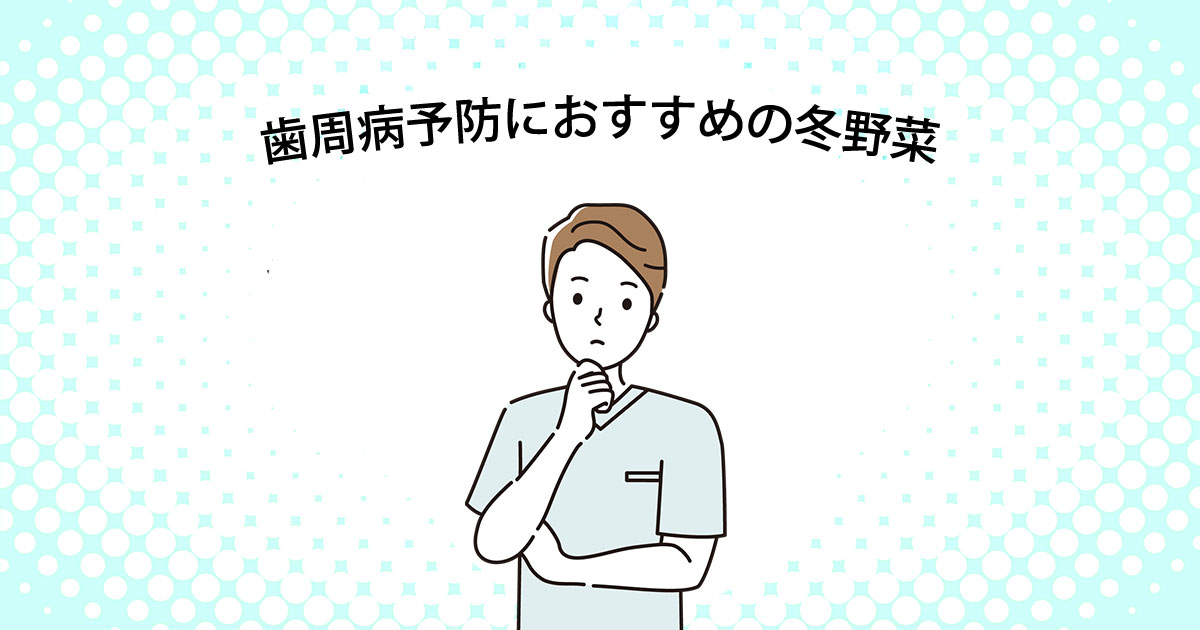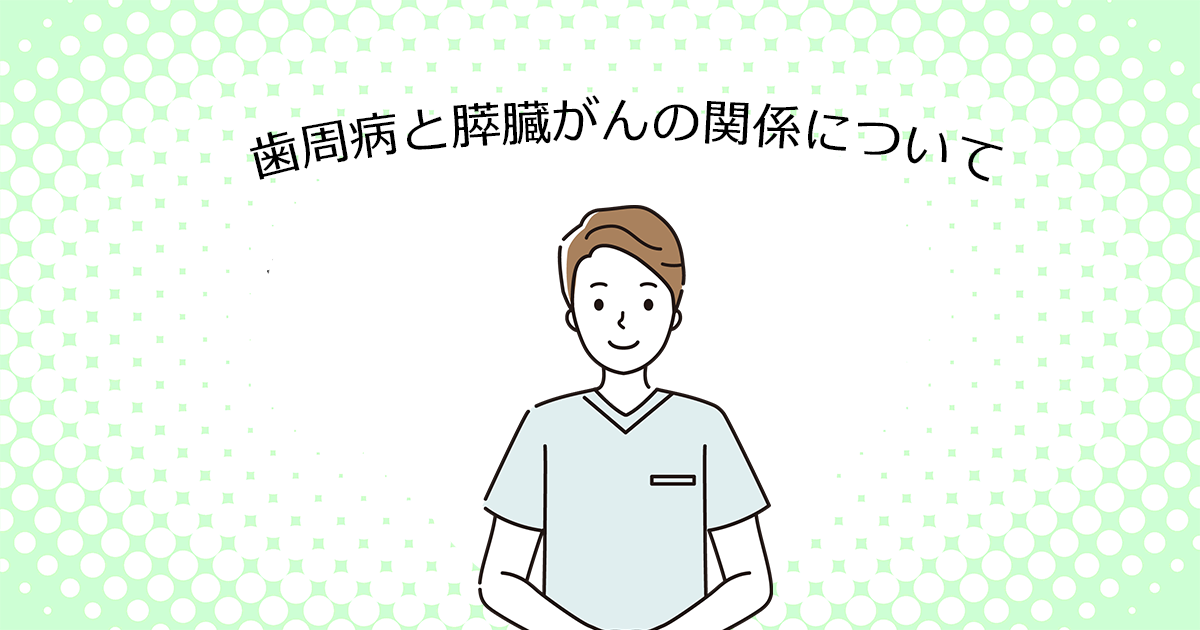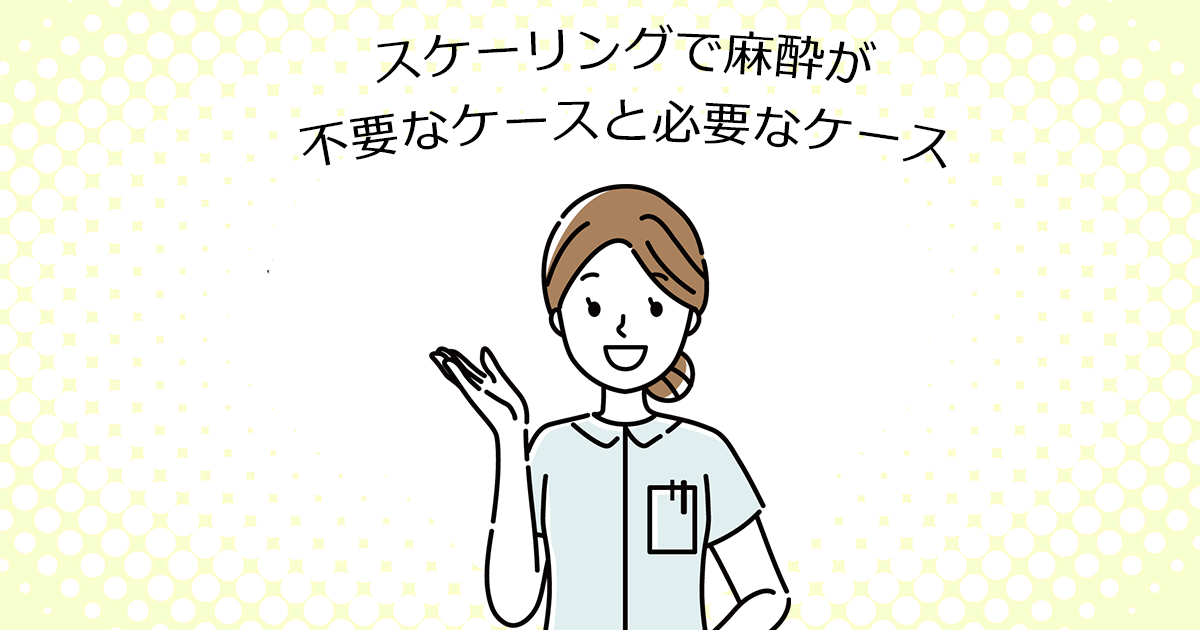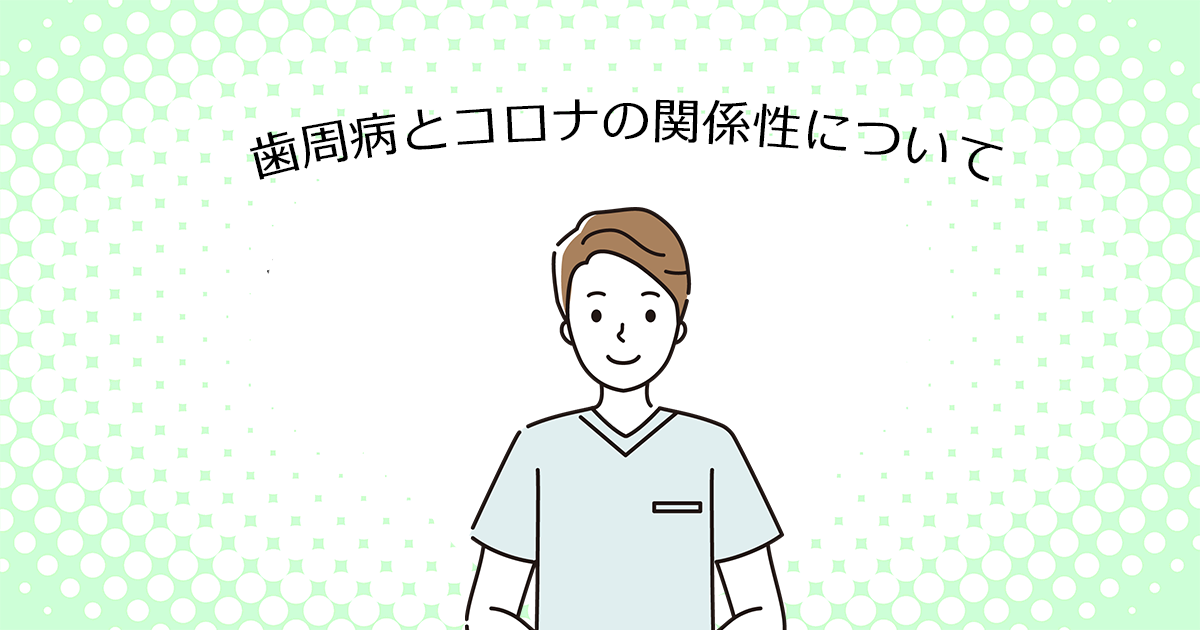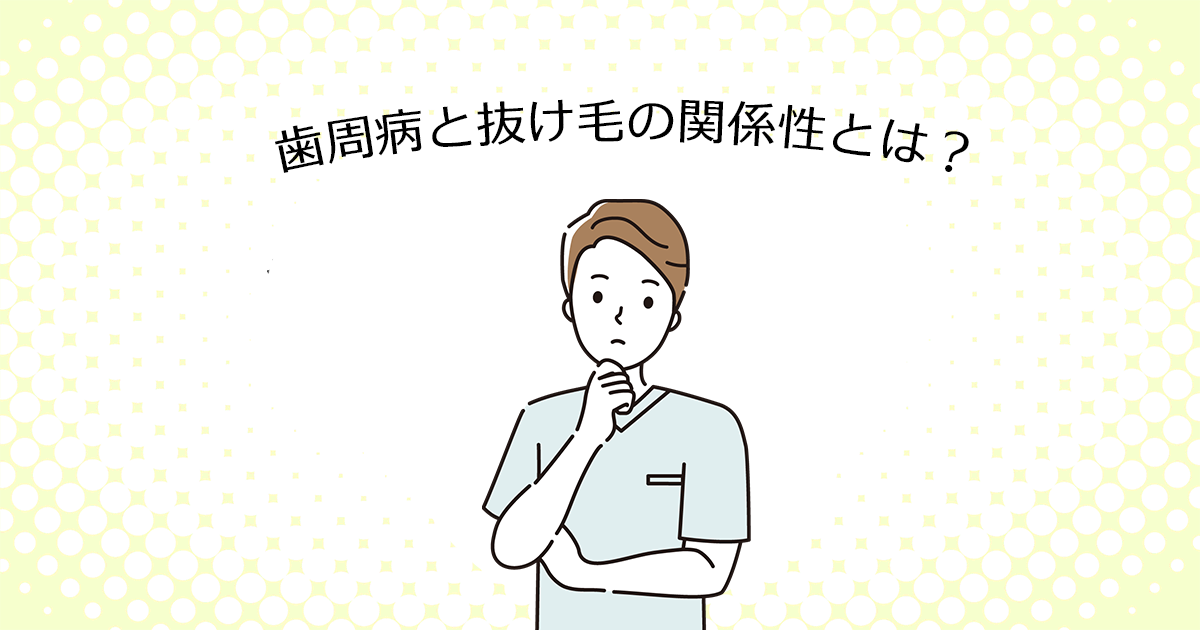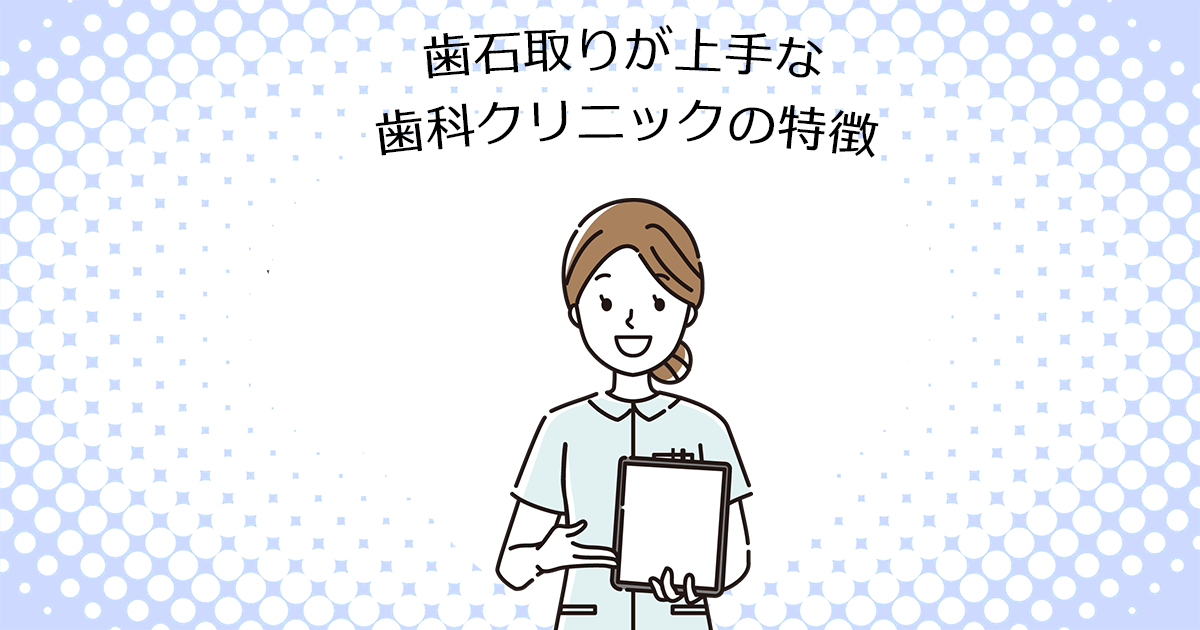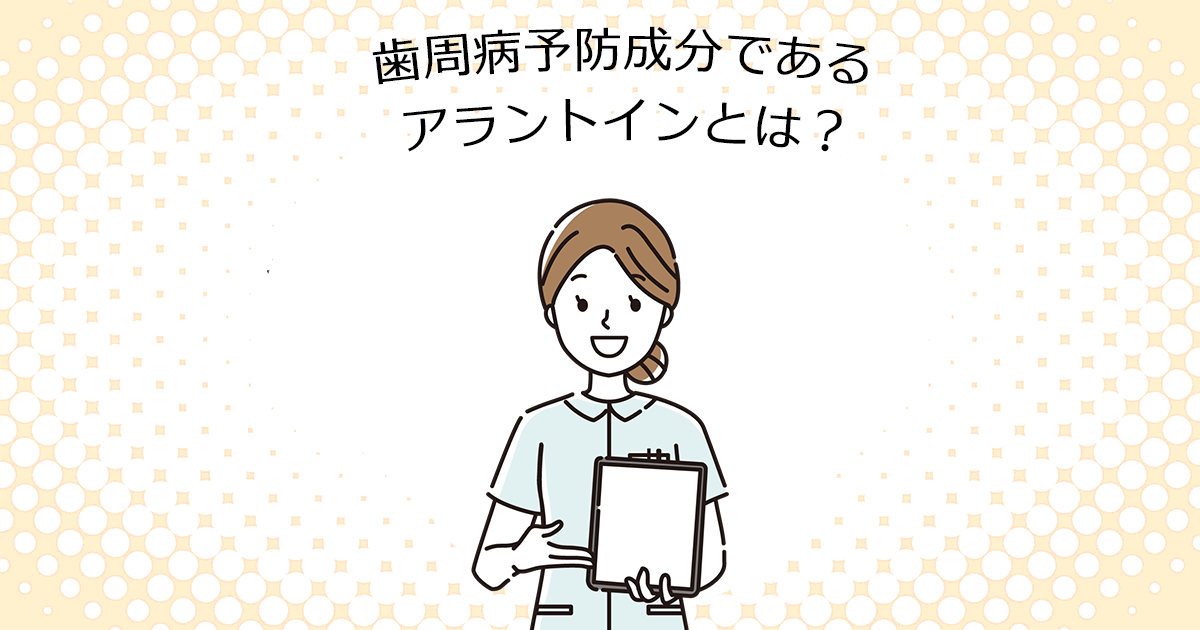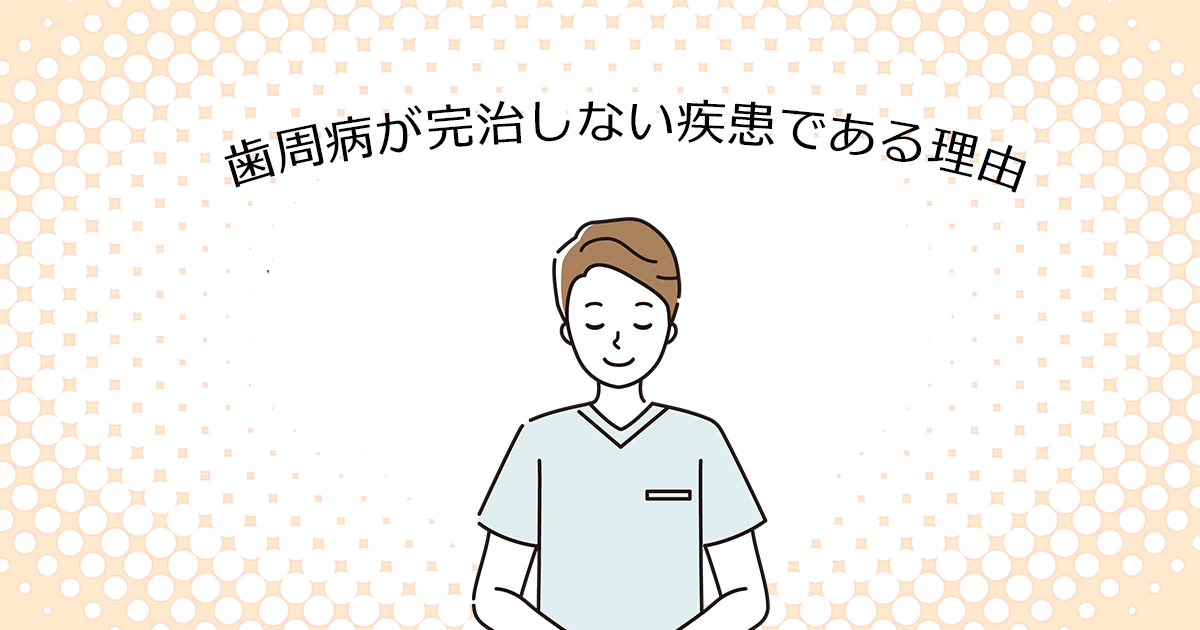睡眠時無呼吸症候群はSASとも呼ばれるもので、睡眠中に呼吸が10秒以上停まる状態が1時間で5回以上続く疾患です。
肥満や扁桃肥大などが原因で起こる閉塞性のものが多いです。
また睡眠時無呼吸症候群は、歯周病共関連性があるとされています。
今回はこちらの内容について解説します。
歯周病と睡眠時無呼吸症候群の相互関係
歯周病と睡眠時無呼吸症候群は、相互関係にあります。
SASの患者さんは睡眠中口呼吸になりやすく、口内が乾燥するドライマウスの状態になります。
そのため唾液による自浄作用や殺菌作用が低下し、細菌が繁殖して歯周病のリスクが2~4倍ほど高まるというデータがあります。
また歯周病による慢性的な炎症は、全身の炎症性サイトカインと呼ばれる炎症物質を増加させます。
こちらが喉や気道の粘膜に影響を与え、気道を狭めることでSASを悪化させる可能性が指摘されています。
歯ぎしりと睡眠時無呼吸症候群の関係
睡眠時無呼吸症候群は、歯ぎしりとの関連性もある疾患です。
SASの患者さんは、無呼吸状態から呼吸を再開しようとする際に、無意識に顎を動かす歯ぎしりを併発することが多いです。
このとき強い力で歯が揺さぶられるため、ダメージはとても大きくなります。
また歯周病がある程度進行している方は、歯と歯茎の密着性が弱まっています。
このような状態で歯ぎしりをしてしまうと、歯をさらに痛めてしまい、やがて歯茎から脱落する原因になります。
推奨されるアプローチ
歯科クリニックでは、睡眠時無呼吸症候群の治療としてスリープスプリントというものが用いられます。
こちらはマウスピースで下顎を前方に固定することで気道を広げ、いびきや無呼吸を改善するというものです。
また歯周病治療を行い、口内環境を整えることで、全身の炎症を抑えSASへの好影響を目指します。
そのためもし睡眠中にいびきをかく、または起床時に口が乾いている場合、歯周病とSASの両面からチェックを受けることが推奨されます。
重度のSASの場合、耳鼻咽喉科や睡眠外来でCPAP治療を受けつつ、歯科クリニックで口腔内を管理する医科歯科連携がとても重要になります。
まとめ
歯周病の方は睡眠時無呼吸症候群を発症しやすくなりますし、逆に睡眠時無呼吸症候群の方も歯周病のリスクが高まります。
またこれらの疾患に共通して言えることは、どちらも自覚しづらいという点です。
そのため、日頃から歯科クリニックなどの定期検診に通い、自身の口内状態や睡眠状態に問題がないかを確認することが大切です。
もちろん、問題があった場合は適宜必要な治療を受けなければいけません。