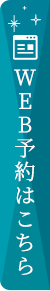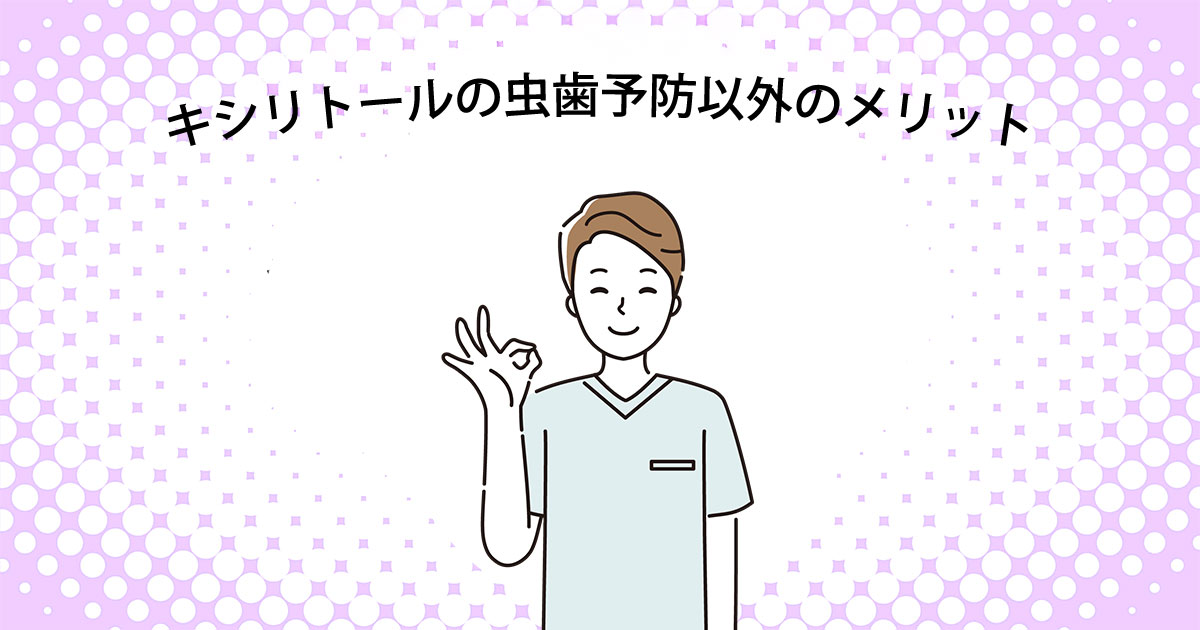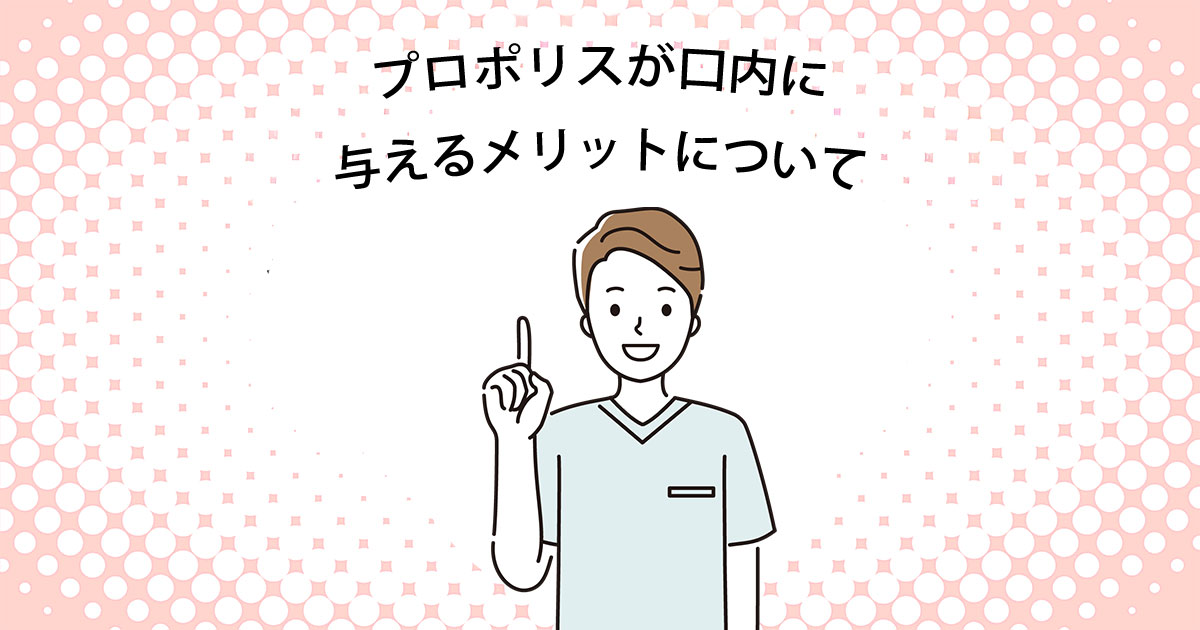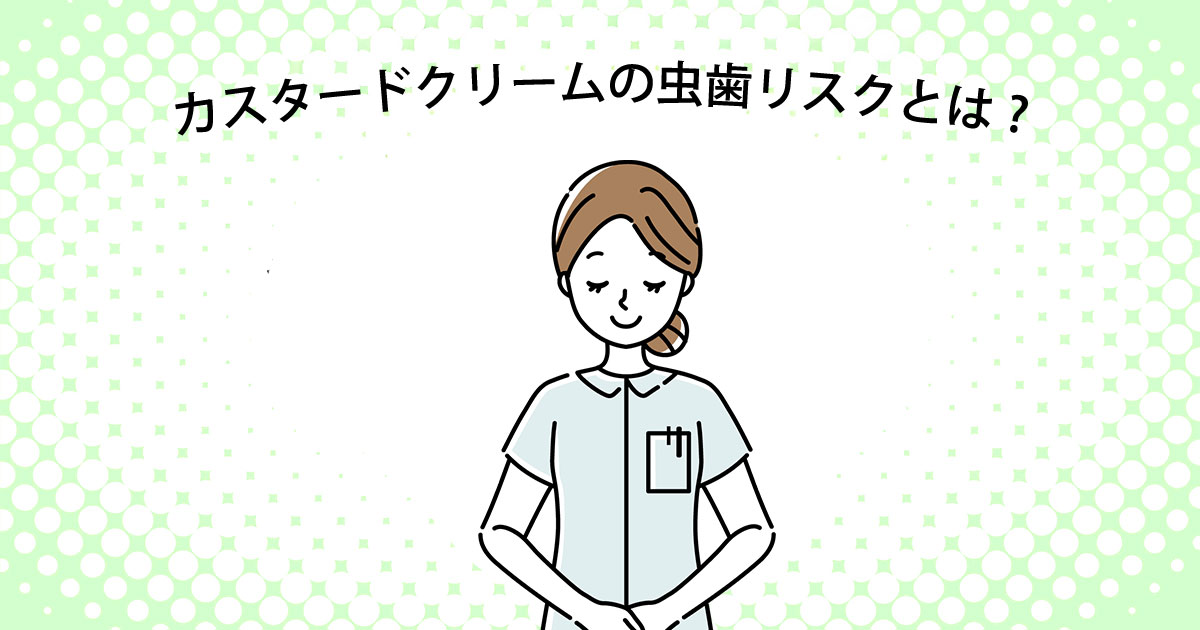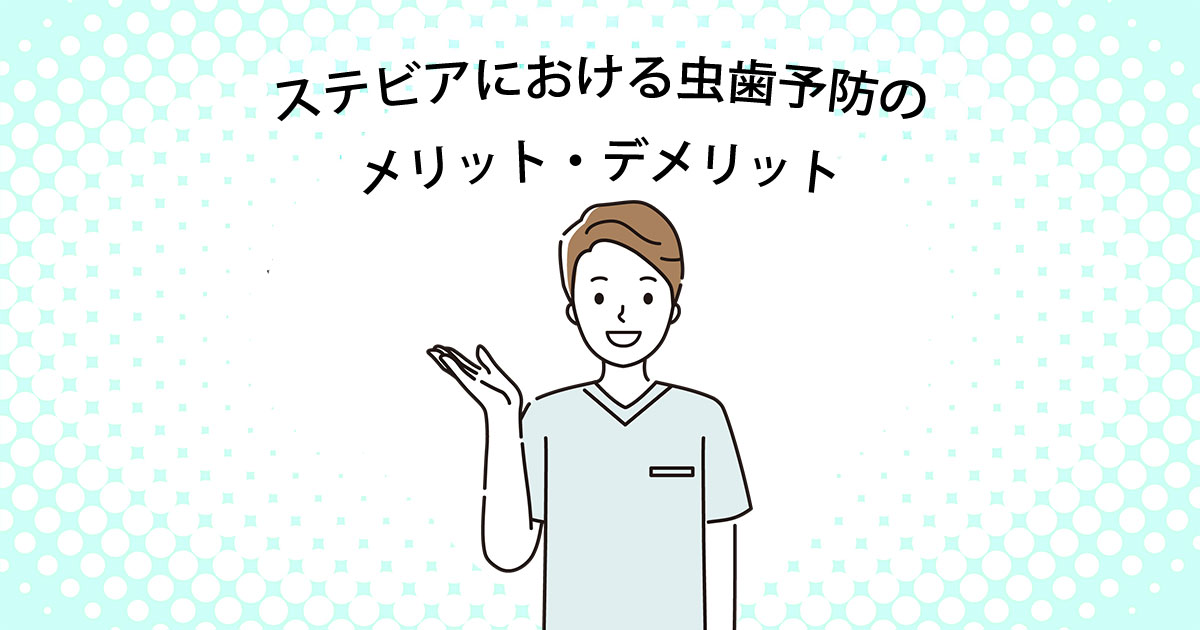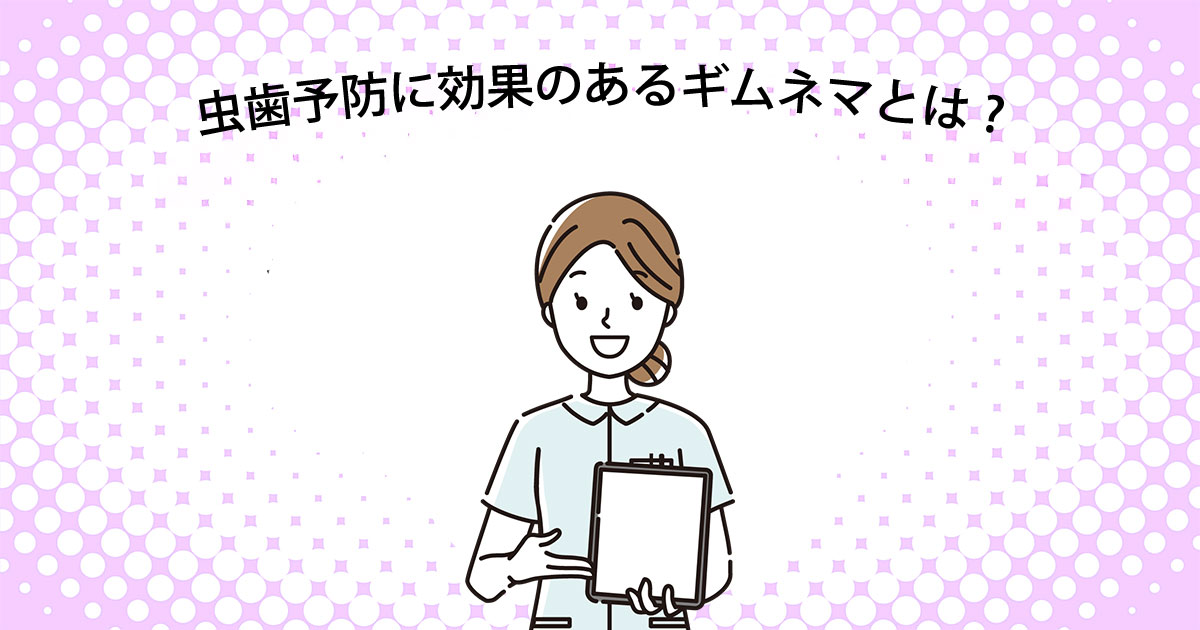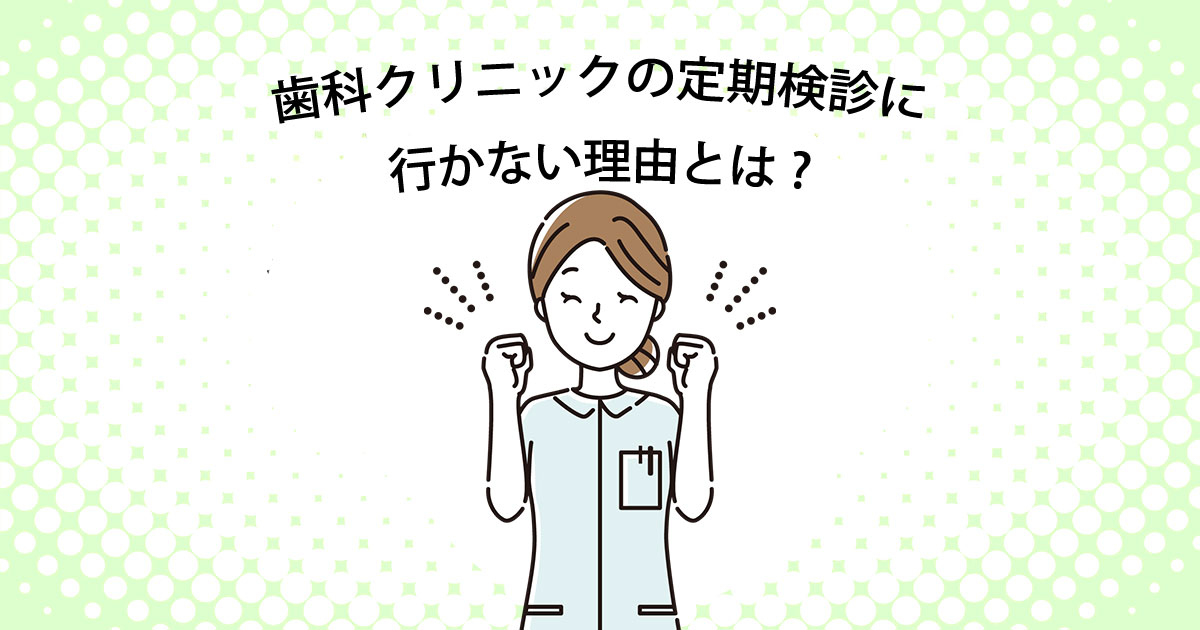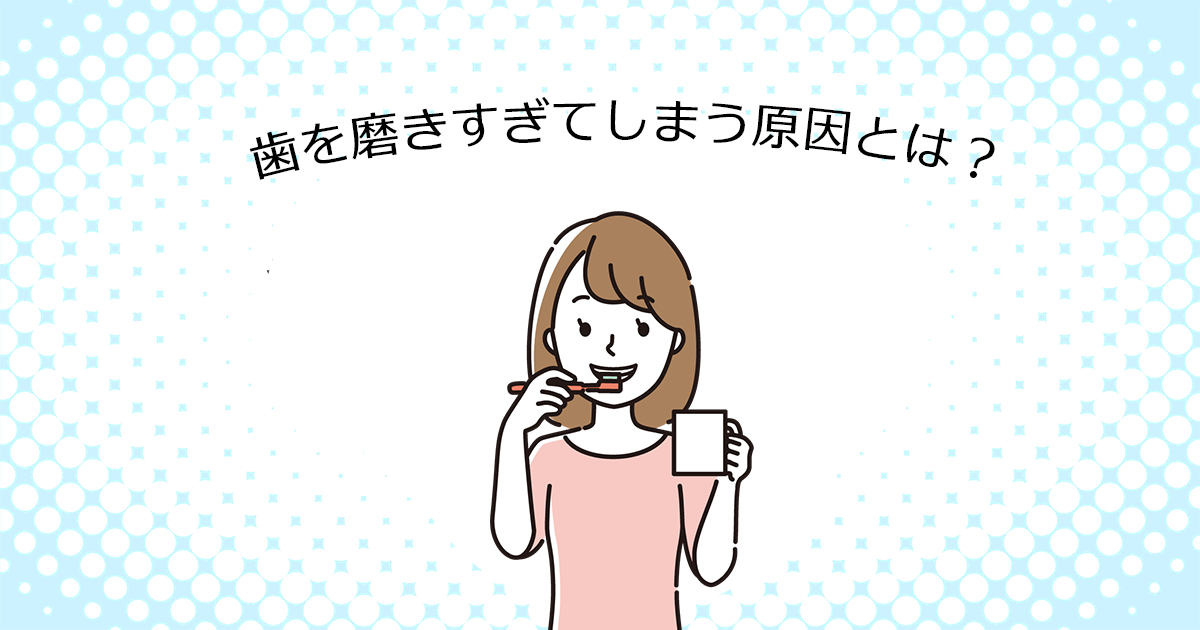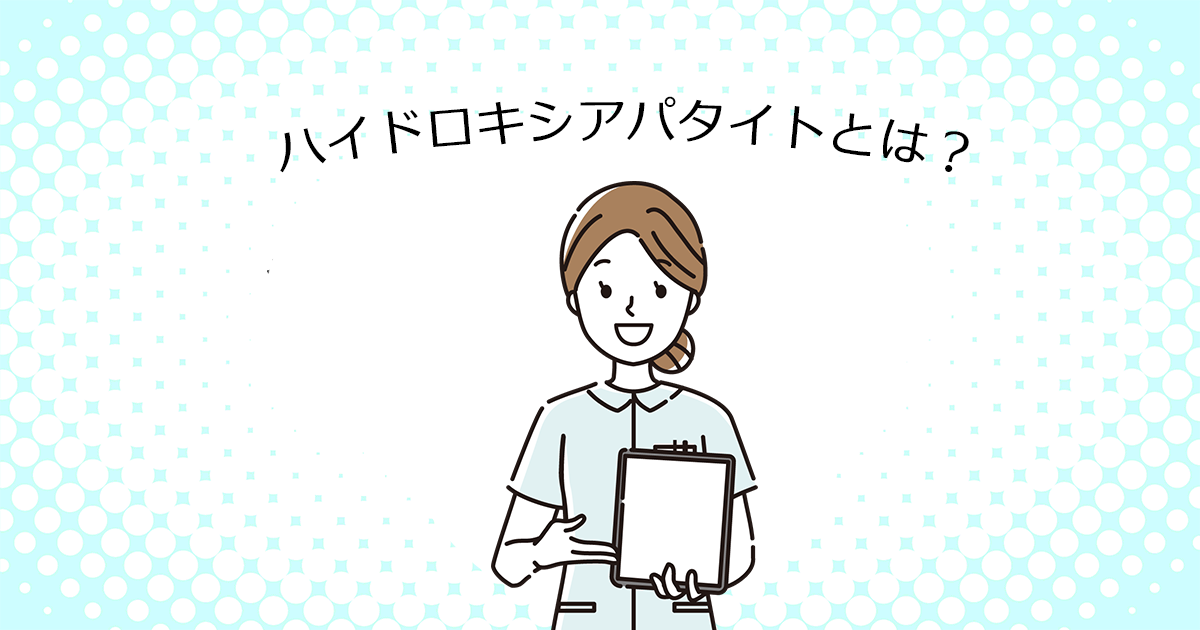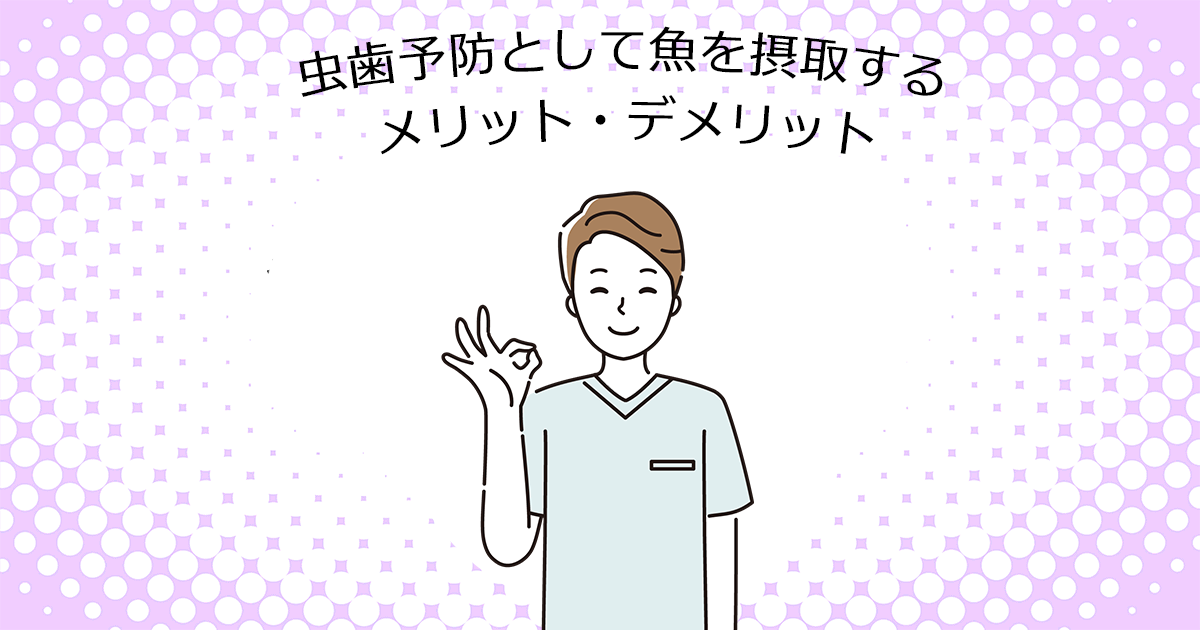キシリトールと言えば、代表的な虫歯予防成分として知られています。
具体的には、虫歯菌が発酵させられないため酸がつくられず、菌の活動を阻害します。
またキシリトールには、実は虫歯予防以外のメリットも数多くあります。
今回は、具体的にどのようなメリットがあるのかについて解説します。
虫歯予防以外の口内環境の改善
キシリトールは、虫歯予防という角度以外からも口内環境を改善してくれるものです。
例えば、歯周病の原因菌となる菌の活動を抑制する効果があるため、歯周病も予防できます。
またキシリトールガムを噛むことで唾液の分泌が促され、口臭の原因となる細菌や食べカスを洗い流す自浄作用が高まります。
さらにプラークの粘着性を下げて歯の表面から剥がれやすくするため、日々のブラッシングによる汚れが落ちやすくなります。
ちなみに、キシリトールは唾液中のカルシウムと結びつき、酸で溶けかかった歯の表面を修復する再石灰化を助け、歯を強くします。
ダイエット、糖質制限
キシリトールのメリットとしては、ダイエットや糖質制限を行う方に有利という点も挙げられます。
キシリトールの甘さは、一般的な砂糖とほぼ同じですが、カロリーは砂糖の約75%しかありません。
そのため、砂糖の代わりにキシリトールが含まれる食品を摂取することで、必然的に痩せやすくなります。
またキシリトールはインスリンを必要とせずに代謝されるため、食後の血糖値の上昇がとても緩やかです。
このことから、糖尿病の方の甘味料としても積極的に利用されています。
その他の意外なメリット
フィンランドの研究では、キシリトールを摂取することで子どもの急性中耳炎の発症率が低下したという報告があります。
こちらは、キシリトールが中耳炎の原因菌の増殖を抑えてくれるからです。
またキシリトールガムの場合、習慣的に噛むことで咀嚼力が向上し、口を閉じる力がつきます。
つまり、口呼吸から鼻呼吸への改善をサポートしてくれるということです。
ただし、一度に大量に摂取すると、体質によってはお腹が緩くなることがあります。
これはキシリトールが小腸で吸収されにくいからです。
まとめ
キシリトールの虫歯予防効果については、多くの方がご存知だと思います。
しかし、実際は虫歯予防を目指す方以外にもおすすめであるため、ぜひ摂取することをおすすめします。
またキシリトールを気軽に摂取できる食品としては、やはりガムが挙げられますが、他にもチョコレートなどさまざまな食品があります。
キシリトール100%の商品であれば、摂取する食品自体は特に何でも構いません。