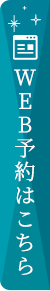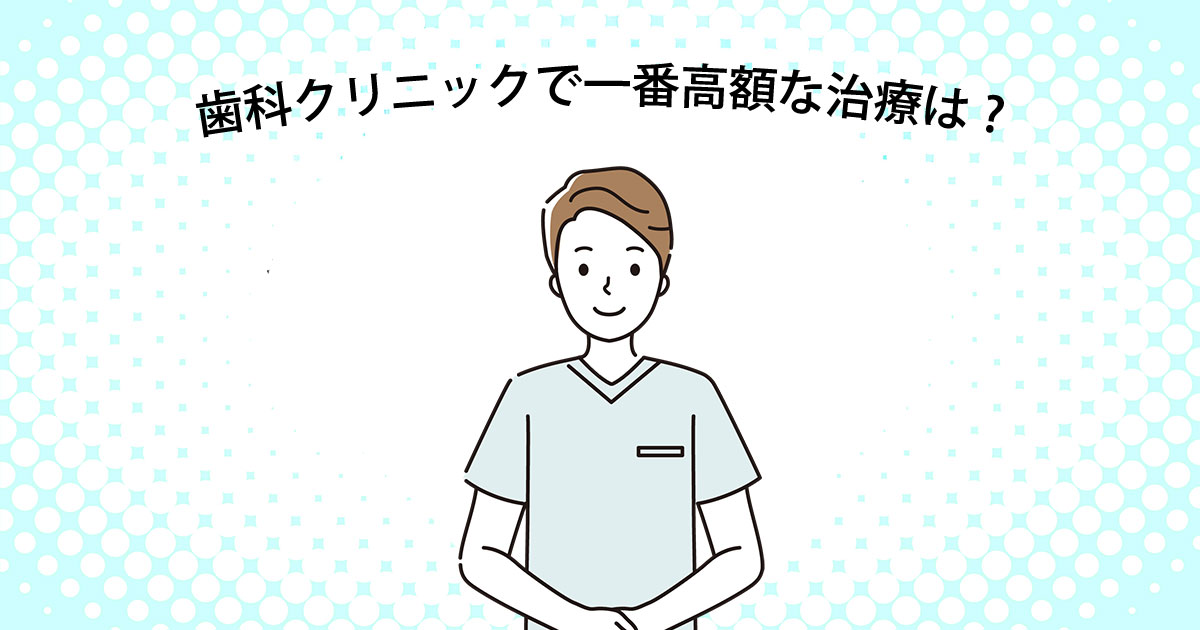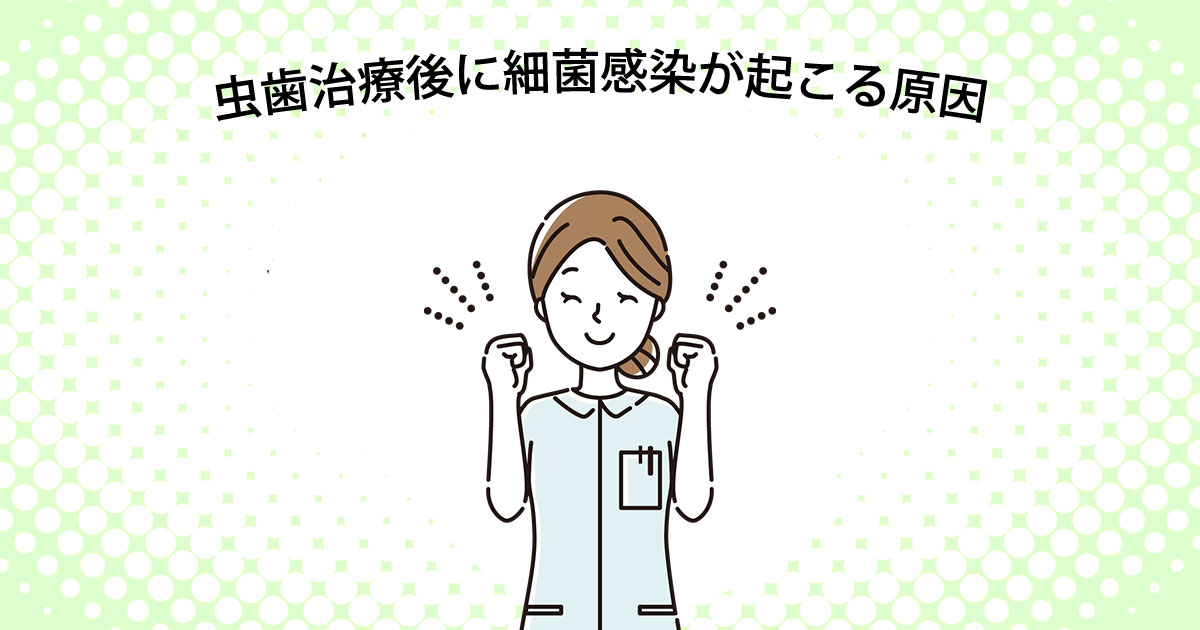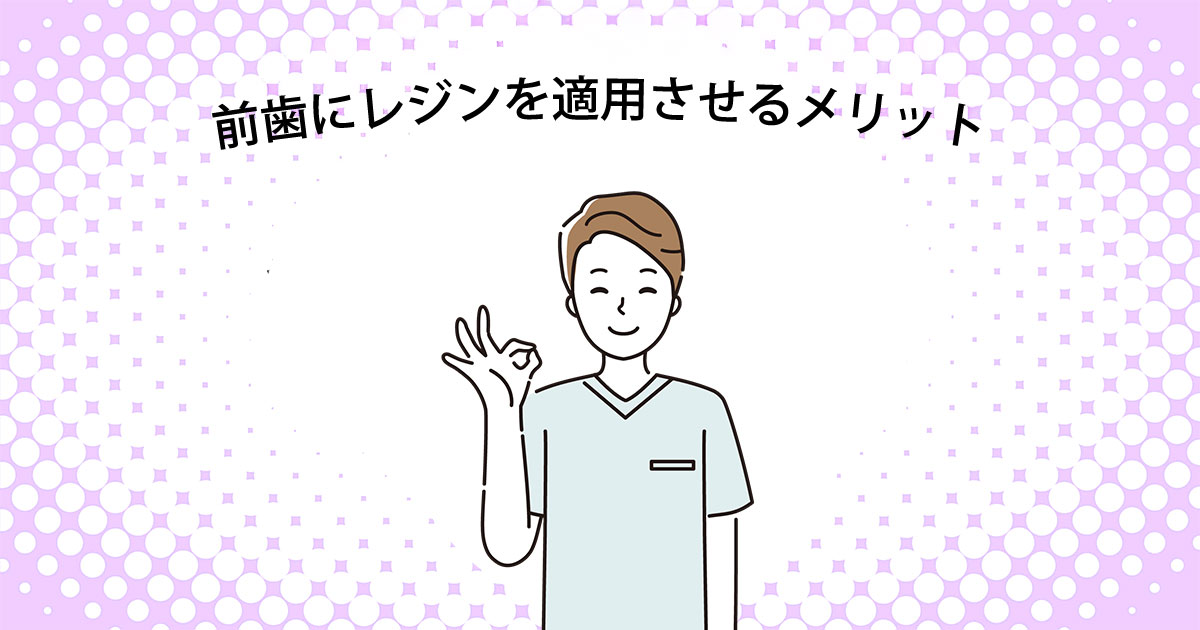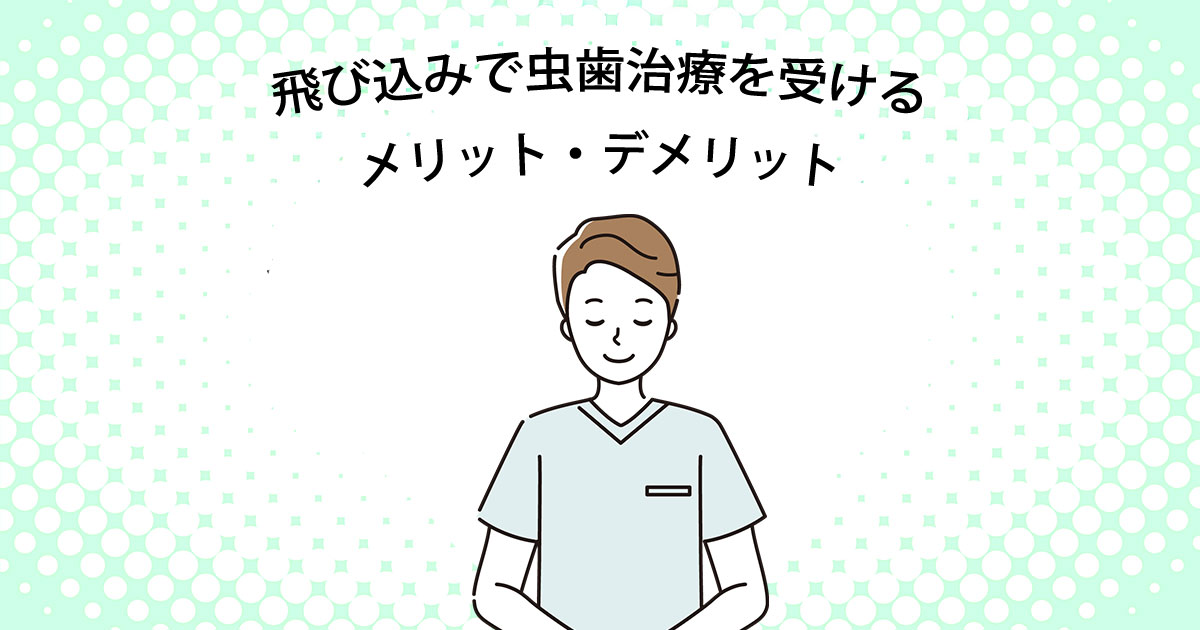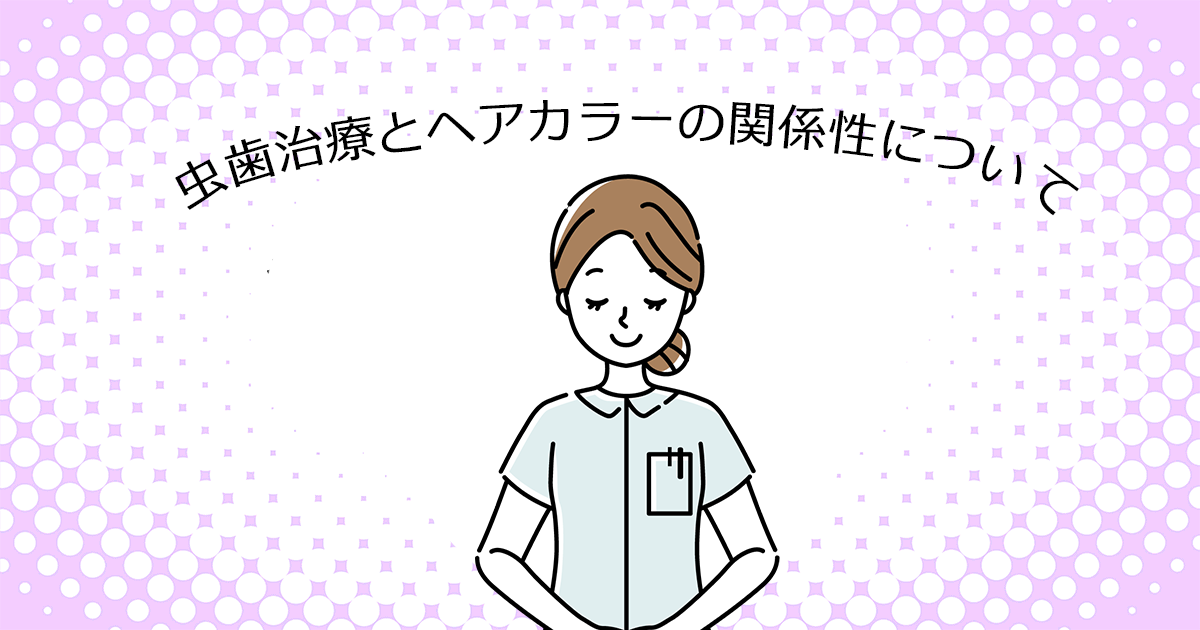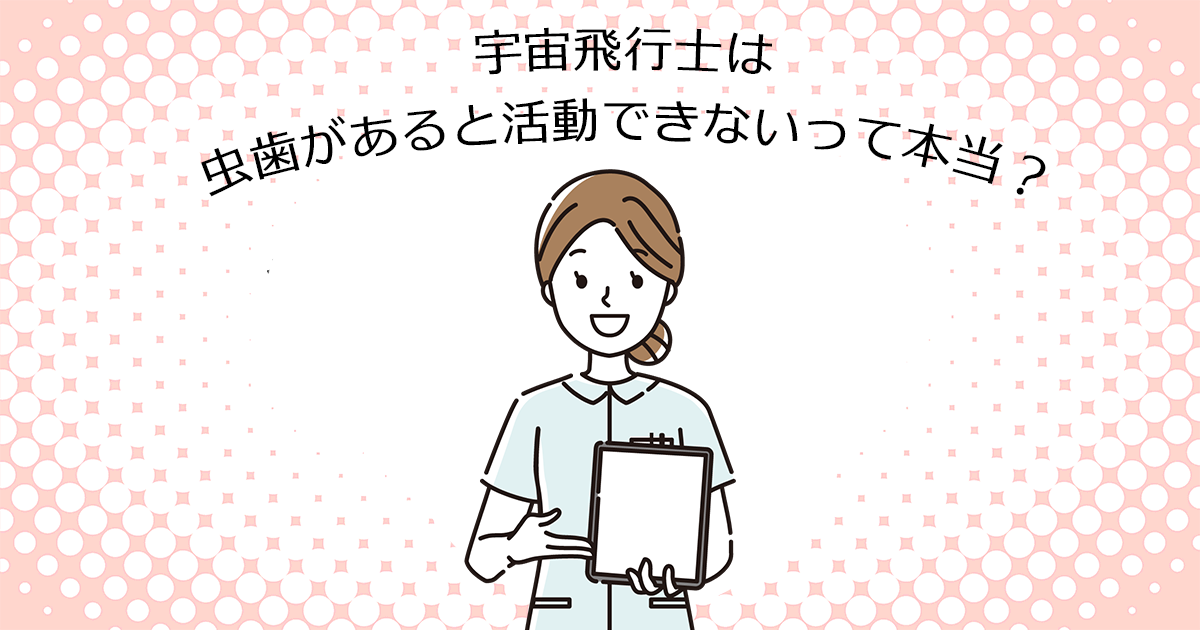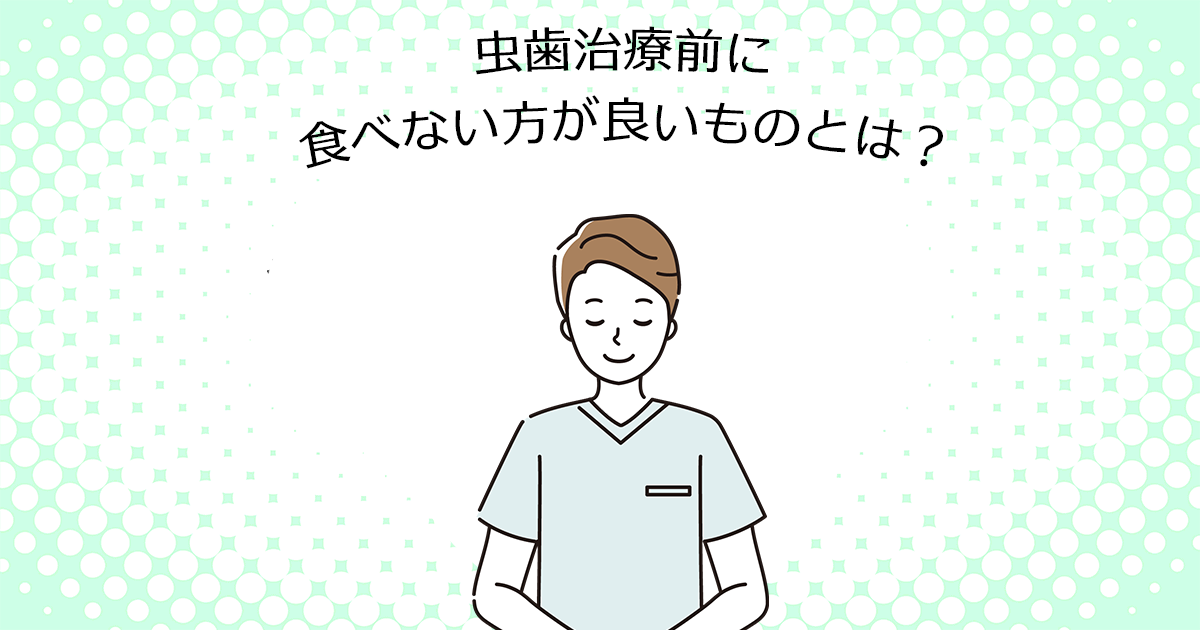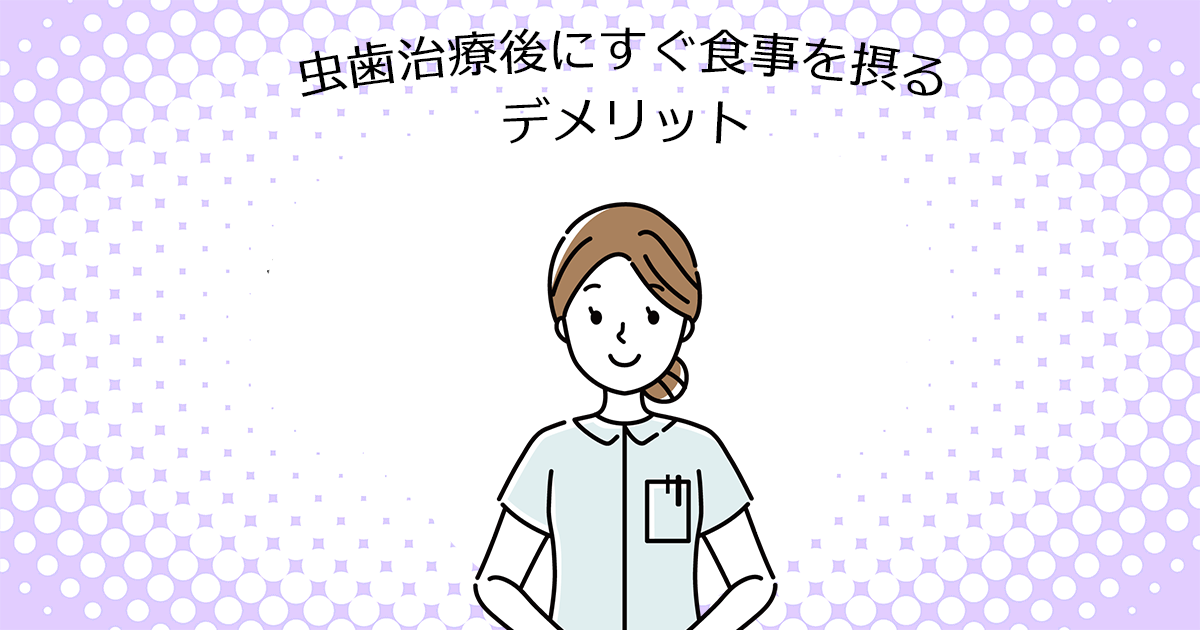歯科クリニックでは、ありとあらゆる治療を取り扱っています。
これらの治療は、大きく保険が適用される保険診療と、適用されない自由診療の2つに分けられ、後者は費用が高くなりがちです。
では、歯科クリニックでもっとも高額な治療は何なのでしょうか?
今回はこちらの点について解説します。
インプラント治療は場合によってはかなり高額
歯科クリニックでもっとも高額な治療は、ハッキリと明言することはできません。
なぜなら、自由診療の金額は各歯科クリニックが決定でき、金額にばらつきがあるからです。
しかしどこの歯科クリニックもかなりの高額で提供していることが多いのは、インプラント治療です。
インプラント治療は、失った歯の代わりに人工歯根を埋め込む治療で、1本あたりの総額は30万~50万円ほどします。
またオールオンフォーという複数のインプラントが連なったタイプは、片顎でも200万~250万円とかなりの金額がかかります。
ちなみに全顎インプラント(20本埋入など)の場合、600万~1,000万円に達する場合もあります。
矯正治療も高額な費用がかかるケースがほとんど
矯正治療は、名前の通り歯並びや噛み合わせを矯正して治す治療です。
矯正治療は、ほとんどのケースで保険が適用されません。
そのため、もっとも一般的で安いとされるワイヤー矯正であっても、60万~120万円ほどかかります。
また目立ちにくいことから人気のあるマウスピース矯正についても、ワイヤー矯正と同じくらいの金額がかかるのが一般的です。
ちなみに、ワイヤー矯正のワイヤーを歯の裏側に装着するリンガルブラケットについては、技術的な難易度が高いためかなり高額になります。
審美性の高い素材を選ぶ場合も注意
例えばセラミックやジルコニアクラウン、ラミネートベニアなどの治療については、1本あたり高くても20万円以下で受けられます。
しかしこちらはあくまで歯1本に対してかかる金額です。
複数本の虫歯を治療するというケースは、決して珍しくありません。
また治療した歯すべてに審美性の高い素材を装着したいという場合、金額は数十万円に上ることも十分に考えられます。
まとめ
歯科クリニックで治療を受ける方は、どうしても金額が気になってしまうかと思います。
特に自由診療を希望する方は、細かい金額がわからなければ怖くて治療を受けられないというケースも多いです。
しかし、金額ばかり気にしていては、適切な治療を受けることはできません。
もちろん金額も考慮すべきですが、一番はやはり歯科クリニックの実績や歯科医師の対応など、特に治療において大事になってくる部分を考慮すべきです。