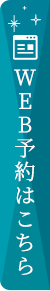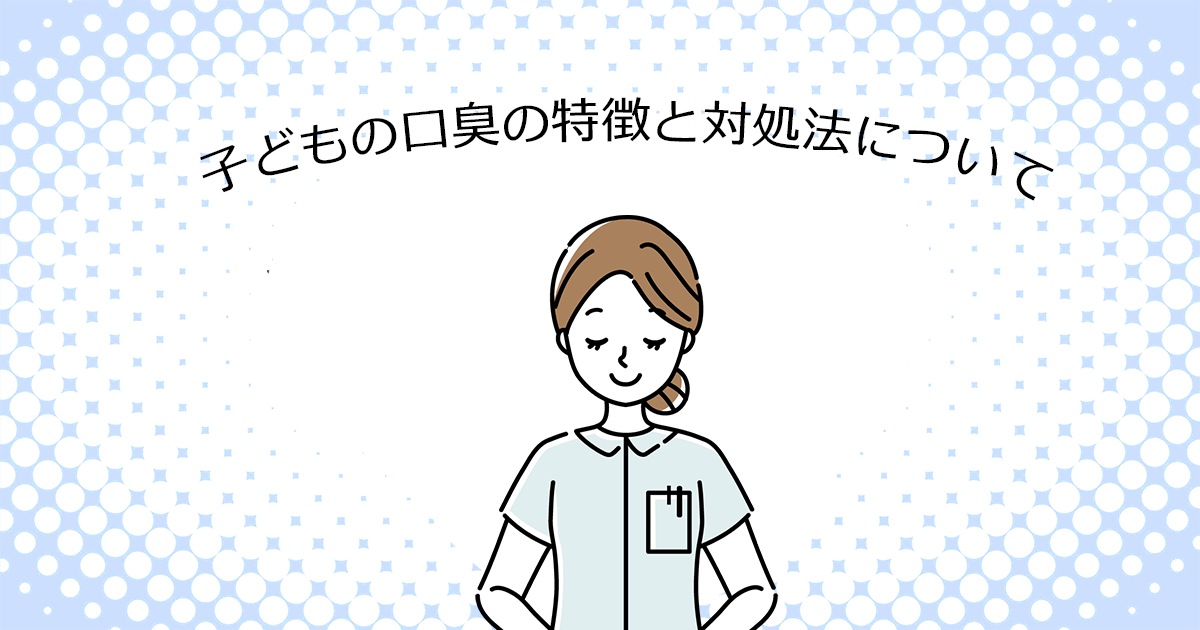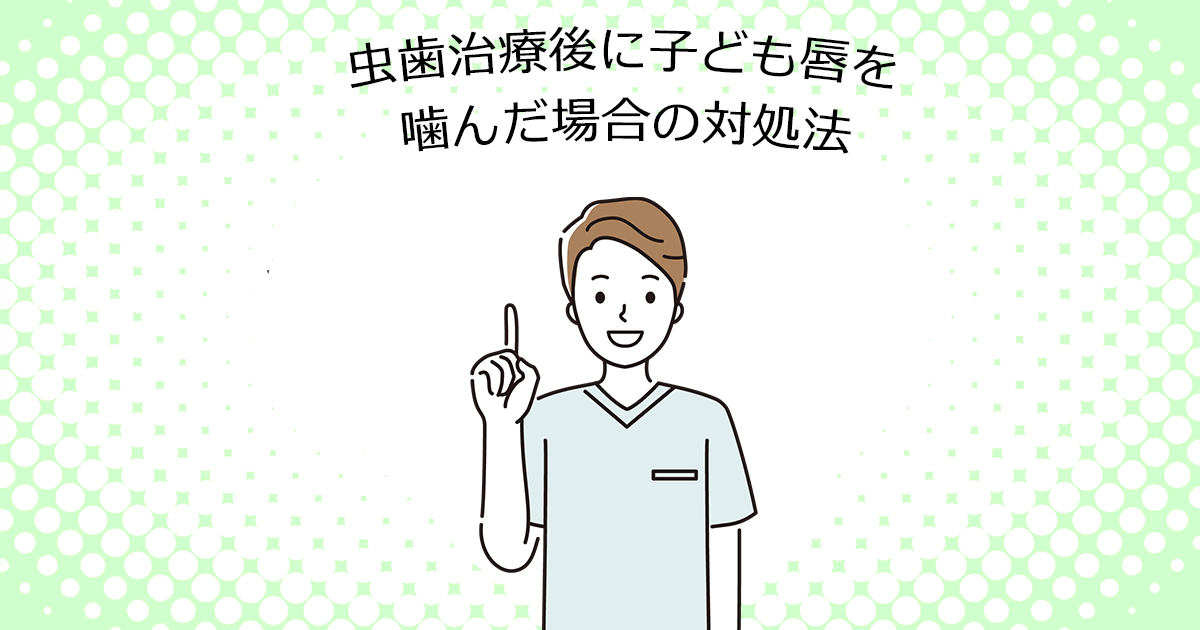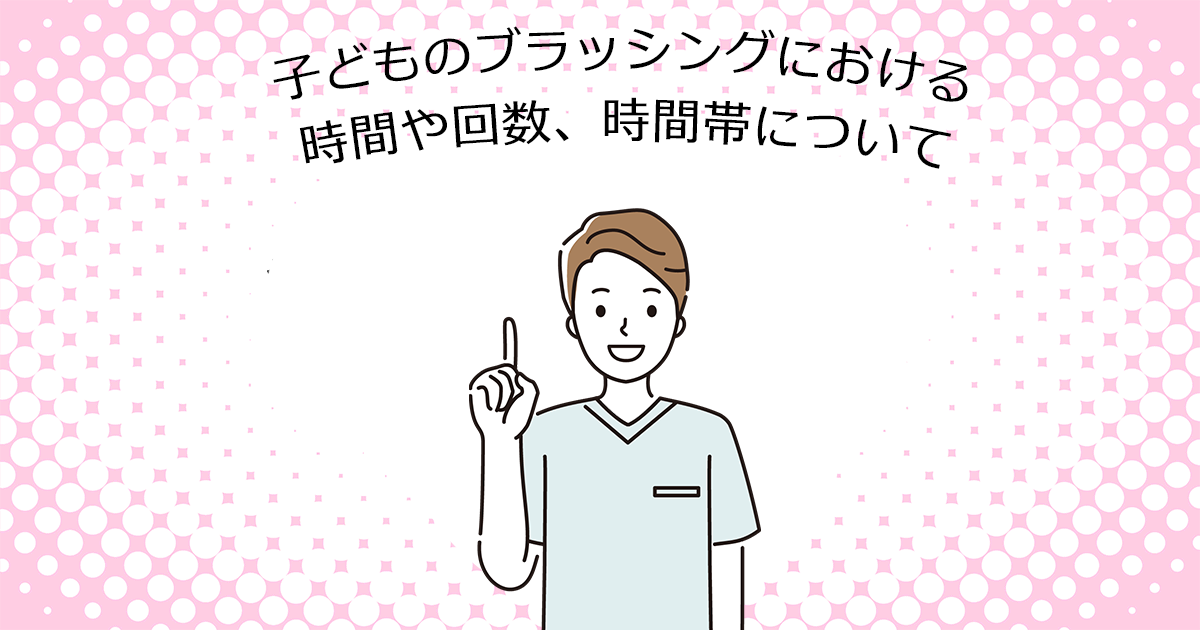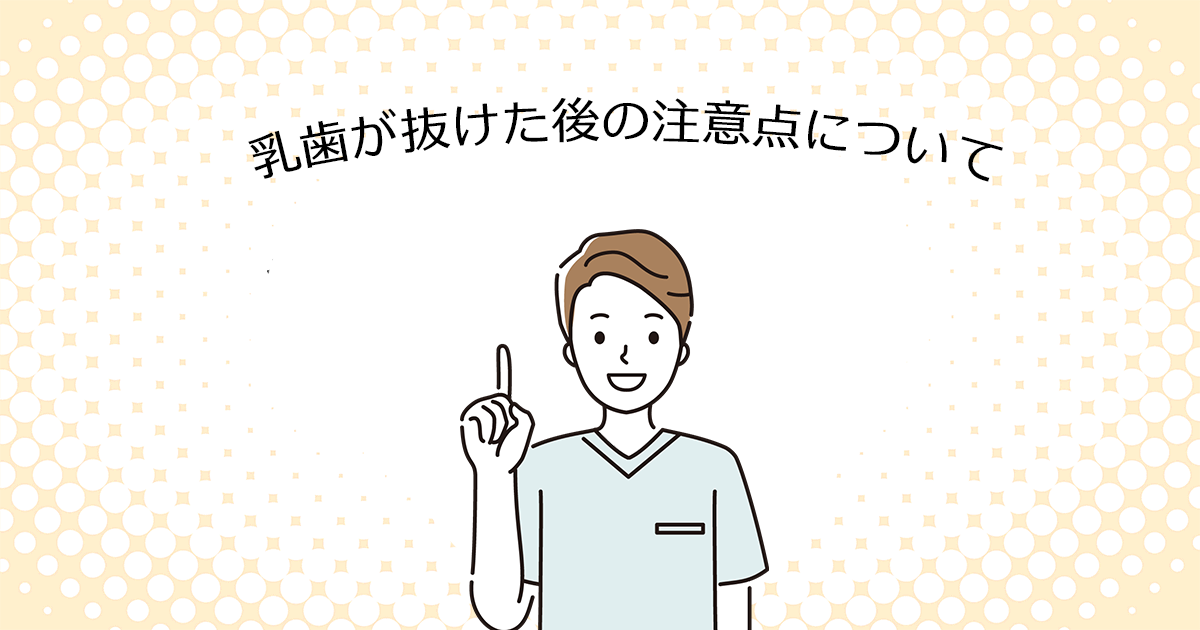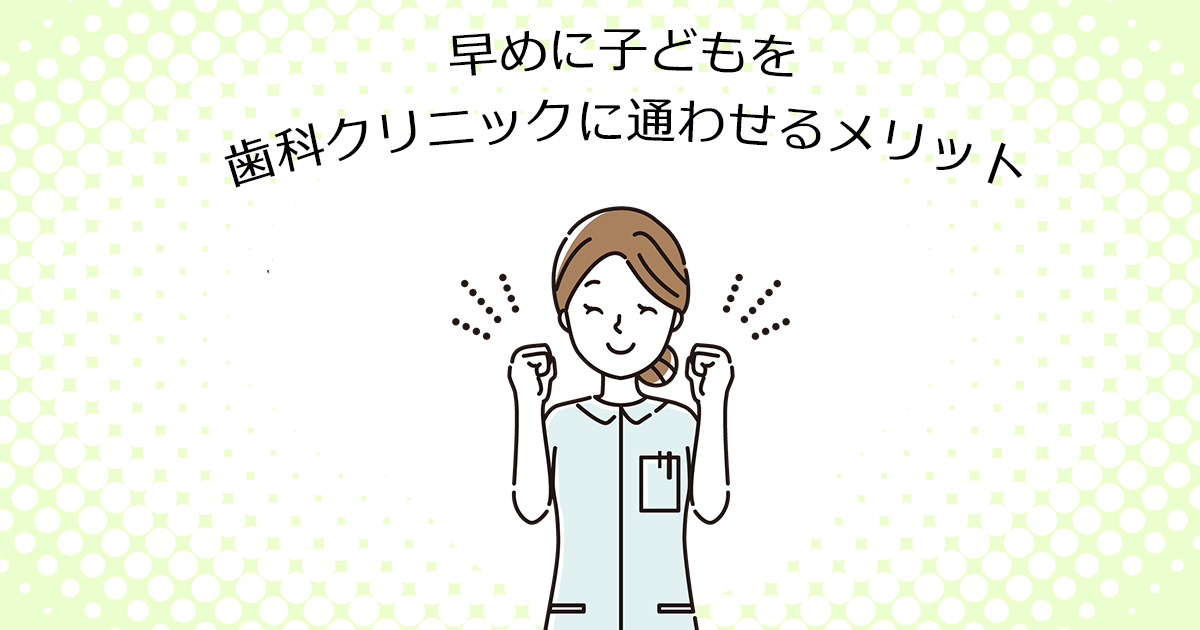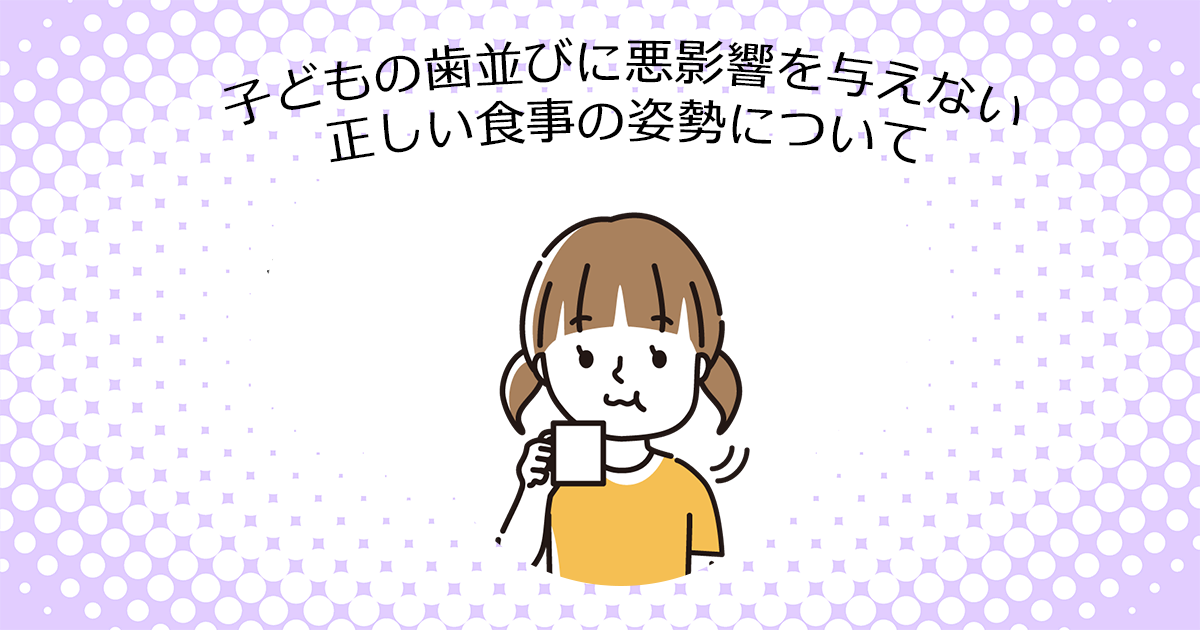少しずつ大きくなってきた子どもを見るのは、親御さんにとって非常に幸せな時間だと言えます。
しかし、それと同時に子どもの成長について、気になる部分も徐々に増えていくものです。
今回は、親御さんが子どもの歯並びを気にし始めるのはいつ頃が良いのかを中心に解説します。
子どもの歯並びを気にし始める時期は?
親御さんの多くは、子どもの歯が生えてきたタイミングから、少しずつ歯並びについて気にし始めるかと思います。
しかし、まだ生え始めのタイミングでは、そこまで歯列全体のバランスについて気にする必要はありません。
意識し始めるのに適しているのは、3歳頃です。
この時期にはほとんどの乳歯が生え揃い、噛み合わせの基礎が出来上がります。
またこの時期に受け口や、上下の歯の大きな隙間などが見られる場合、歯科クリニックに相談すべきです。
さらに6歳頃は、乳歯から永久歯への生え変わりが始まります。
そのため、永久歯が生えるスペースが足りているか、生え方に問題がないかなどを確認することが重要です。
矯正治療を開始する時期は?
子どもの歯並びに異常が見られる場合、親御さんは矯正治療を受けさせることも意識するかと思います。
子どもの矯正治療には第一期治療、第二期治療がありますが、第一期治療を検討するのは混合歯列期の6~10歳頃です。
この時期に行う第一期治療は、顎の骨の成長を正しい方向に導き、永久歯がキレイに並ぶための土台作りやスペース確保を目的としています。
また第二期治療については、すべての永久歯が生え揃う中学生頃から開始します。
こちらはブラケットやワイヤーなどを用いて、歯1本1本の位置や噛み合わせを整えるためのものです。
子どもの歯並びに関するアドバイス
親御さんは子どもの歯並びで気になる点がある場合、自己判断せず定期的にかかりつけの歯科クリニックで相談することが求められます。
そうすれば、専門家による成長段階に合わせたアドバイスを受けることができます。
また子どもの歯並びを気にし始める時期よりも、指しゃぶりや舌癖など、歯並びに悪影響を与える癖がないかを日常的にチェックすることの方が大切です。
まとめ
歯並びは、子どものうちに矯正する方がキレイに整いやすいとされています。
そのため、親御さんは意識し始める時期、矯正治療の開始時期を正確に把握し、適切な対応をしなければいけません。
もちろん、普段の子どもの癖をチェックしたり、歯並びに影響を及ぼすような食事内容を避けたりと、他にもしなければいけないことはたくさんあります。
少しでも悩みがあれば、気軽に歯科クリニックを頼りましょう。